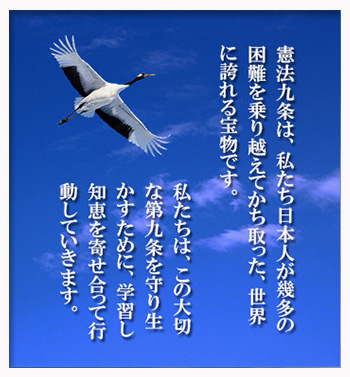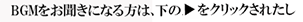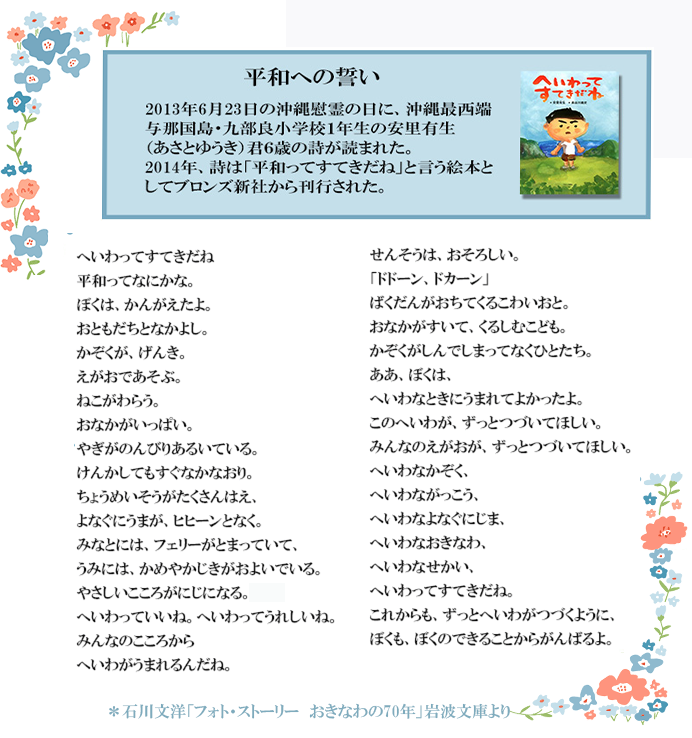
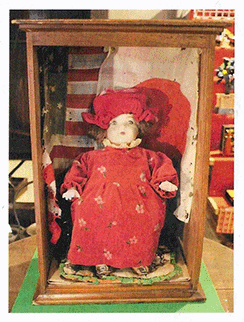
戦争末期、日本の敗戦が近づいていたある日、町内の上級生が家庭にある「青い目の形」を持って学校に集まるようにと回ってきた。
校庭には、近隣の学校や幼稚園からも集められた人形まで積み重ねられていた。親指ほどの小さなキューピーもあった。
小学校の校庭に集まった私たち女生徒が人形を取り囲むと、教練の先生が「アメリカは日本の桜を焼いた。“鬼畜米英”」と叫び、眞刀を振り下ろした。続いて私たちは薙刀(なぎなた)で人形を突くように命じられた。
私は何が何だかわからず、薙刀を足元に落とした。人形に火がつけられた。メラメラと燃え上がる炎に向かって、敵愾心を高揚させるために、私たち一同は軍歌を歌い手をたたいた。
私は心の中で叫んでいた。「先生は人や物を大切にせよと教えたのではないの」と。
「青い目の人形」が親善人形として来日したのは1924年。世界経済悪化の中で、アメリ カでは日本人移民排除の動きが活発化し、「排日移民法」を成立させた。 それと前後して、この動きを心配していたアメリカ人宣教師L.ギューリックが、世界児童親善協会に働きかけ、国際交流によって「平和と友情の精神」を育てたいと願い、日本の渋沢栄一とともに両国の人形交換を思い立ち実現させたのだ。
1924年、アメリカの親子から贈られた心のこもった友情の人形は、壱萬弐千七百弐拾九 (12,729)体。日本全国の希望した小学校や幼稚園に贈られた。青い目をした人形は、名前・住所の入ったパスポートを身につけてアメリカから日本にやってきた。 背丈はおよそ壱尺五寸(約45cm)子供が抱っこするのに良い大きさ。ゆすれば、ママと声をあげお目めも動く。まるで人間の赤ちゃんのようだ。 校長先生も職員も大喜び、人形は校長室や職員室・礼法室に飾られた。私たちの学校では、生徒たちからよく見える階段の最上段に置かれた。
戦時、父兄は戦場に行き、母や姉たちは父や兄たちの代わりに働きに出かけていて、留守の多い家庭が多く、子供たちは寂しく大変な日々を過ごしていた。その中での人形の贈 り物は、どんなに子どもたちの心を温めたことか。 それが、こともあろうに「焚刑」に処されるとは...。
2024年7月、「青い目の人形」処分事件から80年余。 おばあさんになった私は、都会の喧騒から逃れて奥会津只見川流域を旅した。その折立ち寄った「只見、モノと暮らしのミュージアム」で目に飛び込んできたのが、赤いドレスを着た「青い目の人形」の一体。私は思わず駆け寄った。
戦中の軍国主義教育下、言論や行動統制の厳しい時代に、上からの命令に従わず、良識と良心に従って勇気ある行動をとった人々がおられたことに感謝。 全国で処分されなかった青い目の人形は、参百参壱拾七(337)体。贈られてきた青い目 の人形のうちの2.5%だ。
しかし、戦後日本の民主主義と平和は、こうした名もなき人々によって実現され守られている。 今、日本は、アメリカの傘下で、第三次世界大戦に巻き込まれようとしている。 私たちは、どう行動したら良いのだろうか。


日本国憲法は、大日本帝国憲法(明治憲法)と違って、<国民主権>、<平和主義>であ
り、そして<基本的人権>が認められています。
基本的人権の中には<言論の自由>もあります。明治憲法下では天皇(制)を批判する自
由はありませんでしたし、基本的に戦争反対も言えませんでした。江戸時代では幕府批判
など当然許されませんでした。
戦前から民主主義を求める人たちが唱えた「言論の自由」とは、民衆が<お上(為政者・ 権力者)を批判できる>「言論の自由」だったわけです。 明治憲法下、江戸時代以前だって、お上(為政者)は、いつも言論は自由だったわけですから。現代において「言論の自由」は憲法で認められています、が、社会における弱者に対するヘイトスピーチなどは“自由”ではないと思っています。
最近の、事実に基づかない排外的な言動などは許されるものではない、と強く思います。 メディアも権力に対しては大いに言論の自由を発揮してもらいたいですが、庶民に対して は、たとえば、警察が発表したからといって容疑者を顕名で報道するなどはひかえるべき とぼくは思っています。
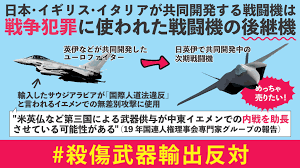
沖縄映画『宝島』(真藤順丈原作)が好評を得ている。沖縄が「アメリカー」であった時期に、米軍占領下の無法・不当な現実の中、「戦果アギャー」の分け前で糊口をしのぐ一方、米兵の金に頼らざるをえない基地の街の女たち。その背後に蠢くヤクザたち。惨たら しく殺される女性や子供たちに心を寄せるが、琉球警察はMPには無力だった。
米軍ジェット機が学校に墜落し大勢の子供たちの命を奪ったことで「祖国」復帰運動が立ち上がる。しかし「アメリカー」はベトナム戦争の深化の中で一層横暴となり、「ウチナンチュー」の怒りが高まり、ついにはコザ暴動となる。
そんな「施政権返還」前の沖縄が描かれる3時間超の作品だが,一気に見入ることができた(ただし水分補給に注意しないと途中トイレに行くのがもったいない)。 コザ暴動の中、基地内に突入したレイとグスクが「武器を取って戦う」か「平和憲法の下に」との口論は、米軍占領下と変わらない 基地の重圧のもとにある今日の現実から、特に「ヤマトンチュー」に問われる。しかも南西諸島は今まさに「戦前」の状態になっていることを、直視しなければならない。
「春夏秋冬緑の島よ」と歌われ(「安里屋ユンタ」)ながら、琉球処分から沖縄戦、戦後の米軍直接支配を経て今も爆音にさらされている島。 『宝島』では、最大の「戦果」が「命どぅ宝」の言葉に含まれていた。
覚書はトランプ大統領が決定した案件に日本が投資しない場合、日本から輸入品に関税を課すこともできると制裁的な処置まで盛り込んでいます。また出資先からの利益分配についても、米国が90%、日本が10%と米国側に一方的に有利なものとなっています。更にリスクが生じた場合は日本が責任を取ることになっています。
民間のエコノミストからも「米国主導、米国優位の性格が強い」と指摘されています。欧州連合(EU)では、米国への投資は民間主導ですが日本では政府系金融機関の国際協力 銀行と日本貿易保険の保障付き公的投資です。投資先など日本側のチェックがほとんど出来ないまま採算がとれない案件がどんどん通る可能性があり投資の焦げ付きにより日本国民の負担が生じる危険性があります。
国際協力銀行法には「日本にとって利益や採算の見込みがない案件には投資できない」と書かれています。9月12日、日本共産党の大門実紀史参院議員は予算委員会で、「焦げ付きが出たら誰が責任を取るのか」と追及しました。赤沢経済再生相は何も答えることが出来ませんでした。
政府系金融は国債と税金などで支えられており巨額のリスクを日本国民が負う恐れがあ ります。このような不平等な取り決めは撤回するしかありません。